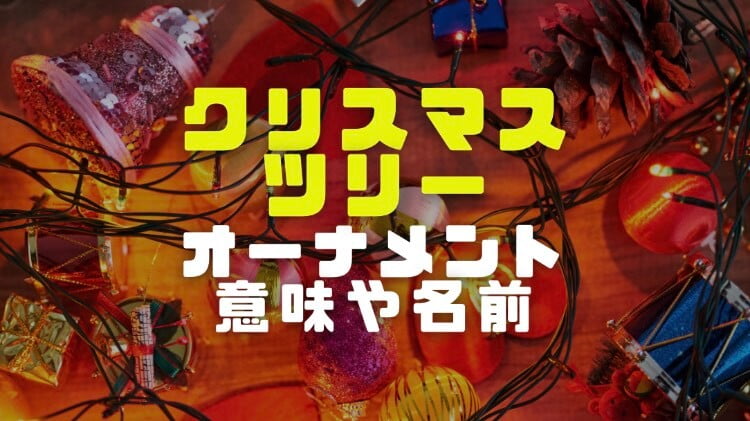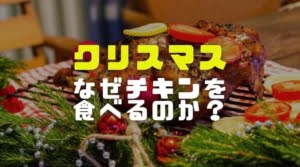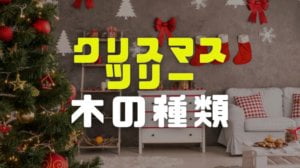クリスマスの時期なると、街のあちこちでクリスマスツリーを見かけますよね。
クリスマスツリーを子供と一緒に飾り付けをするのが毎年の行事になっているご家庭も多いと思います。
なにげなく飾っているクリスマスツリーやオーナメント(飾り)ですが、それぞれに意味や由来・名前があるのはご存知ですか?
サンタクロースやクリスマスケーキ・クリスマスプレゼントなどと並んでクリスマスになくてはならないアイテムのひとつ、クリスマスツリー。
ですが、もともとはクリスマスとクリスマスツリーは関係のないものだったということは意外と知られていないと思います。
クリスマスというのは、キリスト教で「神の子」されるイエス・キリストの降誕を祝う日として、キリスト教徒の間で4世紀半ばから行われていましたが、その当時にはクリスマスツリーという概念は全くありませんでした。
もちろん、聖書の中にもキリストの生誕と何かの木を結びつける記述もありません。
では、どうしてクリスマスツリーが現在のように「クリスマスに欠かせないもの」になったのでしょう?
今回はその意味や由来をみてみます。
[related_posts_by_tax title=”【関連】” posts_per_page=”9″ before_title=”” after_title=”” format=”thumbnails” columns=”3″ taxonomy=”post_tag” link_caption=”true”]
クリスマスツリーの意味
冬になると葉を落としてしまう落葉樹と違い、冬でも青々とした葉をたたえたままの常緑樹は、古くから世界各地で「永遠の命の象徴」とされていました。
またローマ時代には、お祭りの際に常緑樹であるオリーブの枝や木で家の周りを飾り、火を灯し続けることで悪魔が近寄らないようにしたと言われています。
この、冬でも葉を落とさず「永遠の命の象徴」であり、悪魔よけの意味合いもある常緑樹の中でも、クリスマスツリーに一般的に使われているのは「もみの木」です。
クリスマスツリーにもみの木が使われるようになったのには、3つの由来があるとされています。
- 北欧のゲルマン民族のお祭り「ユール」
- フランスの聖人サン・コロンバン
- 中世に行われたクリスマスの演劇
それぞれ説明していきますね。
クリスマスツリーの由来1 北欧のゲルマン民族のお祭り「ユール」
クリスマスが現在のように12月24日に定められた由来となっているのは、北欧に住んでいたゲルマン民族・バイキングの間で冬至の間に行われたお祭り「ユール」だと言われています。
この「ユール」は、キリスト教とは全く関係のないお祭りで、冬至の日に太陽が再び新しく力を持つとされ、この日を「新年」として、北欧神話の神に捧げものをしたり、何日もかけて宴会をしたりしていました。
かたやクリスマスはローマを中心に西暦336年ごろから祝われていましたが、西暦476年にゲルマン人によって西ローマ帝国が崩壊、これを機にクリスマスと「ユール」の融合が図られます。
クリスマスが現在のように12月24日にキリスト教に関係なく祝われるようになったのは、この「ユール」のお祭りとクリスマスを融合させて宗教的な意味合いが薄れたことによるものとも考えられています。
そして、この「ユール」のお祭りの際に使われていたのが、常緑樹である樫の木でした。
樫の木
常緑樹の樫の木は「生命の象徴」として北欧のゲルマン民族たちによって信仰されていて、「ユール」の期間中悪い霊が入ってくるのを防ぐために、家や納屋を樫の木の枝で飾り、そこにリボンを巻いたりたいまつを灯したりしました。
そして、西ローマ帝国崩壊後にクリスマスとの融合が図られた結果、この樫の木の薪をクリスマス前夜に燃やすという習慣がドイツからもたらされました。
この日のために切り出してきた薪にリボンを巻いたり枝で装飾を施して、クリスマスの前夜火を絶やさないようにするという「ユール・ログ(ユールの丸太)」の習慣は、西暦1100年ごろから始まり、フランスやイタリア・北欧諸国にも広まっていきました。
この風習から生まれたクリスマスケーキが、「ビュッシュ・ド・ノエル(Bûche de Noël)」です。
フランスをはじめ、フランス語圏の国々でクリスマス時期に食されているビュッシュ・ド・ノエルについては、別の記事でも触れていますのでよかったら読んでみてくださいね!
▶ クリスマスにケーキを食べるのはなぜ?世界のクリスマスケーキも紹介
北欧のゲルマン民族が冬至のお祭り「ユール」で使っていた樫の木を、クリスマスの日に薪として使い、その際にリボンで飾り付けしていたものが、今のクリスマスツリーの原型と言われていますが、この時点ではまだもみの木ではありませんよね。
この後ヨーロッパで全体にキリスト教の波が広がり、ゲルマン民族もキリスト教への改宗を迫られますが、樫の木への信仰があまりにも強くキリスト教への改宗がなかなか思うように進みませんでした。
そのため、樫の木を同じ常緑樹のもみの木に変え、横から見ると三角形に見えるもみの木は「キリスト教の三位一体を表している」と教えることによって樹木への信仰をキリスト教への信仰心へと向かわせたのだそうです。
もみの木
「キリスト教の三位一体」というのは、「父なる神が頂点で、子と精霊が底辺の両端に位置する」という考え方で、お祈りをするときなどに胸の前で指で三角形を描く、あれですね。
このようにして、クリスマスの日には神聖な常緑樹もみの木を飾り付けるという習慣が人々の間に根付いていったのだそうです。
最初に公にクリスマスツリーが「クリスマスの飾り」として置かれたのは、1419年にドイツのフライブルクでのことでした。
クリスマスツリーの由来2 フランスの聖人サン・コロンバン
クリスマスにもみの木を飾るようになった2つめの由来は、フランスの聖人サン・コロンバン(saints Colomban)の言い伝えによるものです。
フランス北東部の村Luxeuil-les-Bains(ルクスイル・レ・バン)で西暦590年に僧院を築いたサン・コロンバンは、あるクリスマスの夜に、僧侶数人を伴って、近くの山の頂上に登りました。
そこには、大きな古いもみの木があり、キリスト教ではない人々から崇拝されていました。
サン・コロンバンと僧侶たちははそのもみの木に、自分たちのランプを吊り下げ、持っていたたいまつを周りに配置してもみの木の頂上を照らし出しました。
美しく照らされたもみの木を見に村の人々が集まってくると、彼らの前でサン・コロンバンはイエス・キリスト降誕の話をしたのです。
そうして村の人たちをキリスト教に改宗させることができたサン・コロンバンは、その年以降も毎年もみの木をランプで美しく飾り続け、この習慣がいつしかフランスの他の地域にも広まっていったと言われています。
クリスマスツリーの由来3 中世に行われたクリスマスの演劇
古くから、クリスマスの前夜にはイエス・キリストの生誕の様子を演劇にして上演する慣習があります。
今でもキリスト教の習慣が根強いフランスやイタリアではクリスマスに地域や教会で行われていて、本物の馬やロバも動員して村の名物になっているところもあるくらいです。
そんなクリスマスの演劇が中世の教会で行われた際に、演劇の序幕でアダムとイブ(エヴァ)の一幕がありました。
アダムとイブといえば、神様が最初に作った人間で、楽園のようなエデンの園で暮らしていたにもかかわらず、神様が食べてはならないと禁じた「禁断の果実」を食べてしまったことでエデンの園を追い出されてしまうお話ですよね。
その「禁断の果実」を食べたことで、それまで裸で暮らしていたアダムとイブに急に羞恥心が芽生えてしまいますが、この「禁断の果実」を実らせる木は「知恵の木」と呼ばれています。
演劇の中でこの一幕を上演した際に、「禁断の果実」にはリンゴを用いたのですが、クリスマスの時期にはリンゴの木は落葉樹なのであまり見栄えがよくありません。
ということで、代用の木として使われたのが常緑樹のもみの木だったそうなんです。
それ以来、クリスマスの演劇の舞台でもみの木が使われるようになり、徐々にクリスマスの飾り付けとして定着していったそうです。
このように、クリスマスツリーひとつにもいろんな由来があるんですね。
そしていろんな由来が重なって現在のように世界共通のクリスマスの姿が出来上がっていると思うと、なんだか不思議な感じがしますね。
ちなみにクリスマスツリーを飾る習慣がアメリカに伝わったのは19世紀初頭、ドイツからの移民たちによって広められたそうです。
そして日本にクリスマスツリーがもたらされたのは、明治時代。
日本で初めてクリスマスツリーを飾ったのは、銀座の明治屋で、1904年(明治37年)のことでした。
[related_posts_by_tax title=”【関連】” posts_per_page=”9″ before_title=”” after_title=”” format=”thumbnails” columns=”3″ taxonomy=”post_tag” link_caption=”true”]
ここからは、クリスマスツリーのオーナメント(飾り)の意味や由来・名前を紹介します。
紹介するのは以下の7つです。
- トップスター(頂上の星)
- リンゴ・オーナメントボール
- ベル
- キャンディケイン
- ろうそく・電飾(イルミネーション)
- モール・ガーランド
- 雪綿(クリスマス・スノー)
クリスマスツリーのオーナメント1 トップスター(頂上の星)

クリスマスツリーの一番てっぺんに飾る「トップスター」は、イエス・キリストが12月25日未明に生まれた時に、明るく輝いて3人の賢者を導いたとされる「ベツレヘムの星」にちなんでいます。
伝統的にはその家族の中でいちばん年の若い子供がこの星を取り付けることになっています。
また、イギリスなどでは天使をかたどった飾り(クリスマス・エンジェル)をてっぺんに取り付けることもあります。

これらクリスマスツリーのてっぺん飾りの総称を、(クリスマス)ツリー・トップ・デコレーションといいます。
クリスマスツリーのオーナメント2 リンゴ・オーナメントボール

アダムとイブがエデンの園から追い出されるきっかけとなった「禁断の果実」は、ヨーロッパの多くの国でリンゴという解釈をされています。
欧米の国の言葉で「喉ぼとけ」が「アダムのりんご」という名称なのは、喉に禁断の果実のリンゴがつっかえているからという意味なんですね。
クリスマスのツリーの飾りつけに使われるリンゴも、「禁断の果実」のリンゴを表しています。
19世紀ごろまでは、本物のりんごをくくりつけたり、木などでできた作り物のリンゴを飾り付けていましたが、19世紀になってガラス玉が工場生産されるようになり、カラフルなガラス玉(ボール)が使われるようになりました。
最近では光沢のあるメッキのオーナメントボールもいろいろ販売されています。
カラフルなボールの色にはそれぞれ以下のような意味があるとされています。
- 赤:キリストが流した血の色
- 白:純潔
- 緑:永遠
- 金・銀:キリストの気高さや高貴さ
クリスマスツリーのオーナメント3 ベル

イエス・キリストが生まれたことを知らせるために、天使が鳴らしたと言われるベルを意味しています。
魔物を寄せ付けない、聖なるベルとも言われているそうです。
クリスマスツリーのオーナメント4 キャンディケイン

ケインというのは「杖」という意味で、杖の形をかたどったキャンディーや、キャンディーをかたどった飾りです。
羊飼いの持つ杖を表しています。
羊飼いは杖の曲がったところで羊を引っ掛けて群れに戻すことから、助け合いの精神を象徴していると言われています。
また、キリスト教では神=羊飼いで、人=羊とされ、神が杖で人を導くとも考えられています。
赤と白の色は、それぞれキリストの血と、キリストの清い心を表しています。
クリスマスツリーのオーナメント5 ろうそく・電飾(イルミネーション)


光り輝く光は、夜空の星と「世を照らす光」とされるキリストを表しています。
もともとは、牧師さんがもみの木の葉の隙間から見える星空の美しさに感動し、もみの木の葉の隙間にろうそくを立てたのが始まりと言われています。
最近では電飾を使ったものが手軽で安全なことから一般的ですが、LEDを使ったろうそく型の電球も販売されていてとてもいい雰囲気です。

クリスマスツリーのオーナメント6 モール・ガーランド
モールというのは、キラキラふかふかした紐状のもの。

ガーランドは、紐に旗のような飾りが連なったものです。

そして両方が合わさった、モールガーランドというものもあります。

特に、白や銀色の紐状の装飾は、ヨーロッパでは「天使の髪の毛」と呼ばれ、クリスマスの飾りつけによく取り入れられています。

クリスマスツリーのオーナメント7 雪綿(クリスマス・スノー)

北欧の冬至のお祭り「ユール」にも由来しているクリスマス。
冬の森をイメージするために、ツリーに雪を飾ることも多いですね。
この雪のような綿は雪綿(ゆきわた)と呼ばれ、「クリスマス・スノー」という商品名でも販売されています。


この「綿で雪を飾る」作業、けっこうセンスが問われるところですよね。
あんまりボテボテと乗せると重たい感じになってしまうので、ほんの少しを数カ所に乗せるくらいがちょうどいいと思います。
以上、今回は
- クリスマスツリーの意味や由来・名前は?
- クリスマスツリーのオーナメント(飾り)の意味や由来・名前は?
という内容でお送りしました。
クリスマスの靴下の由来についても記事を書いていますので、よかったら読んでみてくださいね!
▶ クリスマスの靴下の由来やプレゼントを入れる意味・置き場所は?
お子さんと一緒にクリスマスツリーのオーナメントを飾る時に、ぜひ意味を話しながら楽しんでみてくださいね!